
何か心に引っ掛かっていたのは、Made in Japanがない(少ない)ということだったようです。
そして、「国の豊かさ」の実現方法への課題感だったようです。
安くて品質の良いものが増えていることを喜ばしく思う一方、その殆どが日本製でないことをどう捉えるかということです。
貿易が出来るのだから、得意な国に得意な財を生産してもらえばよい。自国は自国が得意なことに集中出来るから、その方が効率的なのだ。
これはその通りなのですが、大前提として自国が得意なことで潤っている必要があります。日本は何が得意な国なのでしょうか?
目先の安さだけで、過度に他国に依存するのは危険ではないでしょうか?
安さを追求する過程で、生産だけでなく設計や企画までも移転してしまい、不可逆な産業の空洞化が進展してしまいました。
これは今後、循環型経済へと移行する中で必ず表面化してくると考えています。経済循環を成熟化させていくには国内に、地元にある程度のモノづくりの基盤(モノづくりに臨むヒトづくりを含めて)を残しておかねばなりません。
残念ながら、一度、プロセスが外に出てしまうとノウハウが蓄積されなくなり、能力はさびれてしまいます。これは一つのプロセスだけでなく、連鎖する周辺プロセスへも波及します。
あるプロセスをアウトソースする際の前提は、
中核事業を価値創造の上位レイヤーへシフト出来ること
アウトソースにより内部リソースや残すノウハウとのコンフリクトがないこと
万一の場合もビジネスプロセスが停滞しないように創意工夫で代替ソースが確保されること
だと考えています。
多くの日本企業は、ビジネスモデルを変えることなく、マージンを増やそうとした結果、自らの分身を労働賃金の低い海外に作ってしまいました。
現地企業はノウハウごと移転してもらうと、日本企業に頼らずとも運営が出来るようになり、独立していきます。
その結果、このダイナミズムについていけなかった日本の労働者の職が失われるという自体になりました。そして、日本企業は自らの分身と競争するハメに合うのです。
一見、局所でやっていることに間違いはないようですが、俯瞰してみると、全体として何がしたいのか分からない。
そんな「残念な日本らしさ」を感じることはないでしょうか?
そうならないために上位レイヤー、高次のビジネスモデルをめざしてクリエイションをしていく必要があります。
「モノを売る」から「体験やストーリーを共有した価値交換」へ。点から線そして面へ、さらに3次元、4次元へ。
ゼロから創る必要はありません。そしてこれまでのことを180度変える必要もありません。要素分解して、使えるものを取り出して、組み直して、創意工夫を重ねるのです。
この国にはまだ利用されていないコンテンツがあります。掘り出して、磨いたり、エディットしたり、付加価値を付けて発信する。
そうして紡ぎ出された一つ一つの要素を統合して、コアを作り、その周りに関連要素を配置して、線で結び、ストーリーにするのです。
組み合わせや擦り合わせることで真似できない唯一のサービスが出来るはず。
菌類とその生態系のようなことが出来るといいなぁ、と思います。
Made in Japanがないことを嘆くのではなく、無くなった経緯から学び、次の手を打ちたいと思います。
めざすはMade in Earth with Sustainability、でしょうかね。
なんかいつものように未回収の胞子を撒き散らしながら、話がアッチコッチに行きましたが、一旦、心に引っ掛かっていたことを共有させて頂きました。
それでは。







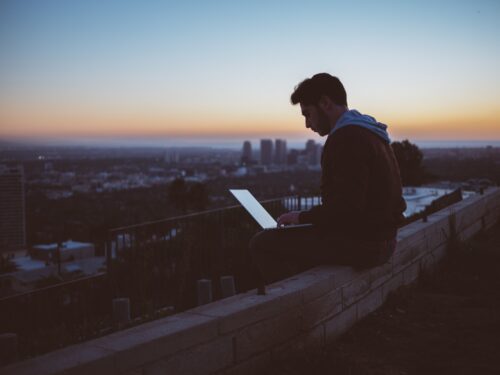
コメント